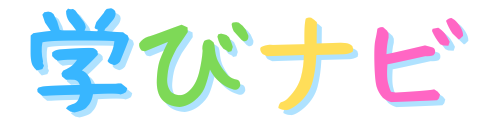1. 授業の基本構成
導入(5~10分)
前時の復習
- 前回の読解内容を簡単に振り返る。
- 物語や説明文の要点を思い出させ、関連する質問を投げかける。
読解への興味を引き出す活動
- 文章のタイトルや挿絵を見せ、「どんな話だと思う?」と問いかける。
- 物語なら登場人物の心情や行動を予想させる。
- 説明文ならテーマについて話し合い、既に知っていることを共有する。
展開(25~30分)
本文の読み取り
- 音読・黙読の使い分け
- 音読でリズムや表現の工夫を感じさせる。
- 黙読で内容の理解を深める。
- 段落ごとの要点整理
- 各段落で「大事なことは何か?」を問いかけ、児童にまとめさせる。
- 図や表を活用し、視覚的に整理させる。
- 登場人物の心情理解(物語文)
- 会話文や行動から登場人物の気持ちを推測させる。
- 「もし自分だったらどう感じる?」と問いかけ、主体的に考えさせる。
- 筆者の意図を読み取る(説明文)
- 接続詞や指示語に注目させ、文と文の関係を理解させる。
- 重要なキーワードを抜き出し、要約する練習をする。
考えを深める活動
- ペアやグループで意見交換
- 物語なら「登場人物の気持ちはどう変わった?」などを話し合う。
- 説明文なら「筆者の伝えたいことは何か?」を共有し、意見を深める。
- 問いを立てる
- 児童自身に「この文からどんな疑問が生まれるか?」を考えさせる。
- 文章を深く読む姿勢を養う。
終末(5~10分)
まとめと振り返り
- 児童に「今日の文章で大事なことは何だった?」と問いかける。
- 物語文なら、登場人物の気持ちの変化や主題を整理する。
- 説明文なら、筆者の主張や要点を簡潔にまとめる。
関連する活動の提示
- 次回の読解につながる問いを投げかけ、継続的な学習を促す。
- 宿題として、本文の要約や感想文を書かせる。
2. 授業のポイント
児童の思考を引き出す工夫
- 「なぜそう思う?」と問いかけ、理由を説明させる。
- 登場人物の視点を変えて考えさせる。
- 言葉の意味を辞書で調べさせる習慣をつける。
読解力を高める指導法
- 重要な部分には線を引かせ、視覚的に整理させる。
- 文章構成を意識させ、どこが大事な部分かを自分で考えさせる。
- 繰り返し出てくるキーワードに注目させ、筆者の意図を探る。
個別対応の工夫
- 読解が苦手な児童には、短い文章での要約練習をさせる。
- 読解が得意な児童には、文章の要点を元に意見文を書かせる。
3. 授業の工夫例
物語文の場合
- 役割音読: 登場人物ごとに分かれて音読し、感情を込めて読む。
- 場面絵を描く: 物語のワンシーンを絵に描き、表現を考える。
- 気持ち日記: 「登場人物になったつもりで日記を書く」活動。
説明文の場合
- 要約チャレンジ: 文章の要点を30字以内でまとめる。
- クイズを作る: 文章内容に関する問題を児童が作成し、互いに出し合う。
- 関連資料を調べる: 文章の内容に関係する図鑑やニュースを調べ、知識を深める。
まとめ
読解力はすべての学習の基礎となる重要なスキルです。児童が文章に興味を持ち、主体的に考えながら読む力を育てることが大切です。多様な工夫を取り入れながら、読解力を高める授業を行いましょう。