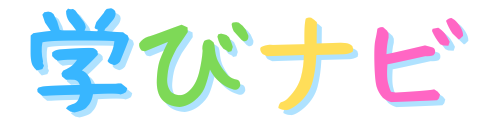1. 授業の基本構成
導入(5~10分)
前時の復習
- 前回学んだ詩や表現技法を振り返る。
- 児童に好きな詩の一節を音読させ、リズムや響きを感じさせる。
詩への興味を引き出す活動
- 挿絵や写真を見せて「この絵からどんな言葉が浮かぶ?」と問いかける。
- 短い詩を提示し、「どんな気持ちになった?」と感想を共有する。
- 身近な言葉を使って、簡単なリズム遊びやことば遊びを行う。
2. 展開(25~30分)
詩の読み取り
音読・リズムを感じる
- 児童に詩を音読させ、リズムや音の響きを体感させる。
- 先生が模範的に朗読し、声の強弱や間の取り方を意識させる。
- 児童同士でペアになり、交互に詩を読み合う。
表現技法を学ぶ
- オノマトペ(擬音語・擬態語)の効果を考える。
- 比喩表現(直喩・隠喩)を見つけ、どのようなイメージを生むのか話し合う。
- 繰り返し表現やリズムの工夫を見つけ、詩の特徴を整理する。
詩の世界を広げる
感想の共有と意見交換
- 「どの部分が好きだった?」
- 「どんな情景が思い浮かんだ?」
- 「どんな気持ちが伝わってきた?」
- 児童の自由な発想を大切にしながら、詩の楽しさを味わう。
3. 創作活動(15~20分)
詩を書いてみる
テーマを決める
- 季節、自然、感情、身近な出来事などをテーマにする。
- 児童に自由にテーマを選ばせ、感じたことを言葉にしてみる。
言葉を集める
- 連想ゲームをして、テーマに関連する言葉をたくさん挙げる。
- 五感(見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わう)を意識して、言葉を選ぶ。
短い詩を作る
- 5行詩、3行詩、1行詩など、短い形から挑戦する。
- 言葉の響きやリズムを意識しながら、自由に表現する。
4. 終末(5~10分)
発表と振り返り
- 児童が自作の詩を朗読し、クラスで感想を共有する。
- 「どんなところを工夫した?」と問いかけ、表現の工夫を意識させる。
- 友達の詩の良いところを見つけ、互いにフィードバックする。
次回へのつなげ方
- 詩の表現技法をさらに深める活動を考える。
- 日常の中で「詩になりそうな言葉探し」をする宿題を出す。
5. 授業のポイント
詩の楽しさを伝える工夫
- 音読を大切にし、声に出すことで詩の魅力を感じさせる。
- 児童の自由な感性を尊重し、正解を押し付けない。
言葉への感受性を育てる
- 音の響き、リズム、イメージを大切にする。
- 五感を使って表現する楽しさを伝える。
個別対応の工夫
- 言葉が出てこない児童には、好きな言葉を1つ選ばせることから始める。
- 表現が得意な児童には、自由なスタイルで長めの詩に挑戦させる。
6. 授業の工夫例
言葉遊びを取り入れる
- しりとり詩を作る(しりとりのルールでつながる言葉を使う)。
- 一つのテーマで連想ゲームをしながら言葉を集める。
音楽や絵と組み合わせる
- 音楽を聴きながら、感じたことを言葉にする。
- 絵を見て、それに合う詩を作る。
共同制作の詩
- クラス全員で1行ずつつなげて詩を作る。
- ペアでお互いの言葉を組み合わせて新しい詩を作る。
まとめ
詩の授業では、言葉のリズムや響きを楽しみながら、自由な表現を育てることが大切です。児童が自分の言葉で感じたことを表現できるよう、楽しく創作できる環境を整えましょう。