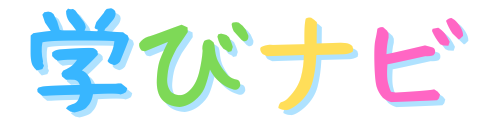1. 器械運動とは
器械運動には、さまざまな種類があり、それぞれ異なる動きを学びます。
- マット運動:前転、後転、側転、倒立、ブリッジ など
- 跳び箱:開脚跳び、閉脚跳び、台上前転 など
- 鉄棒:前回り、逆上がり、足掛け回り、空中逆上がり など
- 平均台(発展学習):バランスを取る、歩行、ジャンプ など
器械運動を通して、身体をコントロールする力や、柔軟性・バランス感覚を養います。
2. 授業の基本構成
導入(5~10分)
前時の振り返り
- 前回の器械運動(跳び箱、鉄棒、マット運動など)の振り返りを行う。
- 児童に「できるようになったこと」「次に挑戦したいこと」を発表させる。
準備運動
- 器械運動に必要な柔軟性を高めるストレッチを行う。
- 体幹を鍛える簡単な運動(ブリッジ、片足バランスなど)を取り入れる。
- 音楽に合わせたリズム運動で、楽しく体をほぐす。
3. 展開(25~30分)
器械運動の技能を高める
基本の動きを身につける
- マット運動:前転・後転・側転の基礎練習。
- 跳び箱:開脚跳び、台上前転のフォームを意識した練習。
- 鉄棒:ぶら下がり、逆上がり、足かけ回りの習得。
レベルに応じたステップアップ
- 児童の習熟度に応じて、段階的に技のレベルを上げる。
- 苦手な児童には補助や簡単な動きから練習をさせる。
- 得意な児童には発展技(連続技や高さを上げるなど)を挑戦させる。
グループでの活動
- 児童同士で動きを確認し合い、よい動きを見つける。
- ペア練習(跳び箱の補助、マット運動のフォーム確認)を行う。
- リレー形式の運動(鉄棒でぶら下がって移動、跳び箱を使った障害物競争など)。
4. 終末(5~10分)
クールダウンと振り返り
- 軽いストレッチで筋肉をほぐし、リラックスする。
- 「今日の運動でできるようになったこと」「難しかったこと」を発表。
- 友達の良かった動きを見つけ、お互いにフィードバックする。
次回へのつなげ方
- 「次はどんな技に挑戦したい?」と考えさせ、学びを継続させる。
- 家庭でできる簡単なストレッチや筋トレを紹介し、継続的に体を鍛えられるようにする。
5. 授業のポイント
器械運動の楽しさを伝える工夫
- 児童が達成感を味わえるよう、小さな目標を設定する。
- ゲーム要素を取り入れ、楽しみながら器械運動を学ぶ。
- できたことを発表し合い、自信を持たせる。
児童の成長に合わせた指導
- 個々のレベルに応じた練習方法を用意する。
- 苦手な児童には補助や補強運動を取り入れ、成功体験を積ませる。
- 得意な児童には応用技や組み合わせ技を挑戦させる。
個別対応の工夫
- 跳び箱が苦手な児童には、段を低くして練習させる。
- 鉄棒の逆上がりができない児童には、補助具や補助者を活用する。
- マット運動が苦手な児童には、回転感覚を養う練習から始める。
6. 授業の工夫例
動きを分解して学ぶ
- 跳び箱:助走→踏み切り→手のつき方→着地の順に動きを確認。
- 鉄棒:ぶら下がる→蹴り上げる→回転するの順に分けて練習。
- マット運動:前転・後転のスムーズな回転を意識しながら、動作を分解する。
協力しながら運動を楽しむ
- ペア練習:お互いにフォームを確認し、アドバイスをし合う。
- グループ発表:できる技を組み合わせて、演技を作る。
- 器械運動リレー:マット・跳び箱・鉄棒を使った障害物コースをクリアする。
ICTを活用する
- 動画を使った運動学習:見本の動画を見て、動きを理解する。
- タブレットで自分の動きを確認:撮影してフォームを分析する。
- スローモーションで動きを研究:鉄棒や跳び箱のフォームを細かくチェックする。
まとめ
器械運動の授業では、児童が「できた!」という達成感を味わいながら、安全に運動できる環境を作ることが大切です。一人ひとりの成長を大切にしながら、楽しみながら技術を習得できる授業を展開しましょう。