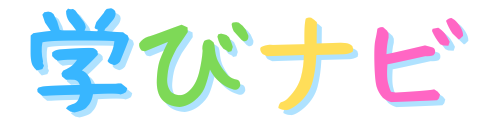1. 体つくり運動とは
体つくり運動は、運動能力の基礎を育てるための運動です。さまざまな動きを経験しながら、柔軟性・バランス・持久力・瞬発力を向上させます。
- 柔軟性を高める運動:ストレッチ、ヨガ、しなやかに体を動かす運動
- バランス感覚を養う運動:片足立ち、平均台歩き、スラックライン など
- 持久力を鍛える運動:持久走、ジャンプ運動、サーキットトレーニング など
- 瞬発力・敏捷性を鍛える運動:ダッシュ、ジグザグ走、リレー など
- 協力・対戦を通じた運動:ペア運動、チーム対抗ゲーム、リレー など
これらの運動を組み合わせ、児童が楽しく体を動かせる授業を行います。
2. 授業の基本構成
導入(5~10分)
前時の振り返り
- 前回行った運動や活動の振り返りを行う。
- 児童に「どんな動きが楽しかった?」「次は何を頑張りたい?」と問いかけ、意欲を引き出す。
準備運動
- 体を温めるために、簡単なストレッチや動き作り(ラジオ体操、軽いジョギングなど)を行う。
- 音楽を活用しながら、リズムに乗って体をほぐす。
- 友達とペアになり、楽しく準備運動を行う。
3. 展開(25~30分)
体の動きを高める運動
さまざまな動きを経験する
- 基本的な動き(走る・跳ぶ・回る・バランスをとる)を組み合わせた運動。
- 動物の動きをまねる運動(カエル跳び、クマ歩きなど)。
- リズムに合わせた運動(ダンスやジャンプを取り入れた動き)。
体力や柔軟性を高める活動
- 簡単なサーキットトレーニング(マット運動・なわとび・平均台など)。
- 柔軟運動を取り入れたゲーム(しっぽ取り、バランスゲームなど)。
- 持久力を高めるための楽しいランニングゲーム。
協力・対戦を通じた運動
- ペアやグループでの運動(ボール渡し、協力してバランスをとる活動)。
- チーム戦を取り入れた運動遊び(リレーや障害物競争)。
- 勝敗をつけない運動(全員で達成する目標を決めてチャレンジする)。
4. 終末(5~10分)
クールダウンと振り返り
- ゆっくりとした動きでストレッチを行い、心拍数を落ち着かせる。
- 「今日の運動で楽しかったこと」「できるようになったこと」を話し合う。
- 友達とペアになり、お互いに良かった点を伝え合う。
次回へのつなげ方
- 「次回はどんな動きをもっと練習したい?」と考えさせ、学びを継続させる。
- 体を動かす楽しさを実感し、家庭でもできる簡単な運動を紹介する。
5. 授業のポイント
体を動かす楽しさを伝える工夫
- ゲーム形式を取り入れる:楽しく体を動かせるように、競争や協力型の活動を増やす。
- 多様な動きを経験させる:ジャンプ・回転・バランスなど、さまざまな動作を組み合わせる。
- 音楽を活用する:リズムに乗って体を動かすことで、楽しさを引き出す。
児童の成長に合わせた指導
- 体力や運動能力に応じた段階的な指導を行う。
- 苦手な児童には個別に声をかけ、運動への抵抗感を減らす。
- 運動が得意な児童には、発展的な動きを取り入れチャレンジの機会を与える。
個別対応の工夫
- 運動が苦手な児童には、簡単な動きから取り組ませ、自信をつけさせる。
- 得意な児童には、新しい技やコンビネーションを考えさせる。
- グループ活動では、異なるレベルの児童が協力できるように工夫する。
6. 授業の工夫例
運動のバリエーションを増やす
- 道具を活用する:なわとび・フラフープ・ボールを使った楽しい運動。
- 動きの工夫:片足ジャンプ、スキップ、ジグザグ走など、変化を加えた運動。
- 環境を変える:体育館、校庭、芝生など、異なる環境での運動を取り入れる。
協力しながら楽しむ活動
- ペアでのミッション:2人1組で動きを合わせてゴールするゲーム。
- クラス全員でのチャレンジ:大縄跳びやボールパスをみんなで協力して成功させる。
- 障害物リレー:チームで協力しながらコースをクリアする。
ICTを活用する
- 動画を使った運動学習:動きの見本を見ながら練習する。
- タブレットで動きを確認:自分の動きを録画して改善点を考える。
- 運動記録アプリを活用:走った距離や跳んだ回数を記録し、成長を実感する。
まとめ
体つくり運動の授業では、児童が体を動かす楽しさを感じながら、運動能力を高めることが大切です。ゲーム性や協力活動を取り入れ、誰もが楽しく参加できる授業を展開しましょう。