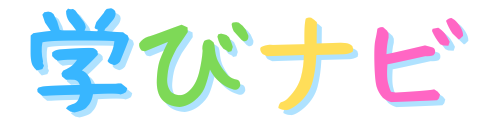1. 水泳運動とは
水泳運動は、水の中での動きを学びながら、浮く・進む・潜るといった基本的なスキルを身につける運動です。小学校の体育では、以下のような種目を学びます。
- 浮く運動(背浮き、クラゲ浮き):水にリラックスして浮かぶ感覚を養う。
- 蹴る運動(バタ足、ドルフィンキック):水を蹴る力を鍛え、進む感覚を身につける。
- 進む運動(クロール、平泳ぎ、背泳ぎ):基本的な泳法を習得し、スムーズに進む。
- 潜る運動(けのび、潜水):水の抵抗を感じながら、息を止める感覚を学ぶ。
- 水の安全を学ぶ(浮き身、救助法):万が一の時に安全に対応できるスキルを身につける。
水泳運動を通じて、水への恐怖心をなくし、体全体を使ってスムーズに動く力を養います。
2. 授業の基本構成
導入(5~10分)
前時の振り返り
- 前回の水泳練習で習ったことを振り返る。
- 「水に慣れるために大切なことは?」「どんな動きをすると進みやすい?」と問いかけ、児童に考えさせる。
陸上での準備運動
- 水泳に必要な柔軟性を高めるストレッチ。
- 腕回し、足のストレッチを行い、関節の可動域を広げる。
- 呼吸の練習(ゆっくりとした深呼吸、水の中での息継ぎを意識する)。
3. 展開(25~30分)
水泳運動の技能を高める
水に慣れる運動
- 水中歩行:水の中で歩き、浮力や抵抗を感じる。
- 水かけ遊び:顔や体に水をかけ、リラックスする。
- 浮く練習:背浮きやクラゲ浮きで水に身を任せる。
進むための基本練習
- バタ足:キックの基本を学び、水の上で足を動かす。
- けのび:手を伸ばし、まっすぐ進む感覚を身につける。
- 息継ぎの練習:顔を水につけたり上げたりしながら、リズムよく息をする。
泳ぎの基本動作
- クロール:腕の動きと息継ぎの連携を練習する。
- 平泳ぎ:蹴り足と手の動きを意識しながら習得する。
- 背泳ぎ:リラックスしながら、後ろ向きに進む感覚を養う。
応用・ゲーム活動
- リレー形式の泳ぎ:チームで協力しながら泳ぐ。
- 浮き身を利用した安全技術の練習:水の中で力を抜き、楽に浮く方法を学ぶ。
- 水の中でのボール遊び:水中での動きに慣れ、楽しみながらスキルを向上させる。
4. 終末(5~10分)
クールダウンと振り返り
- ゆっくりとした動きでストレッチを行い、筋肉をほぐす。
- 「今日の授業でできるようになったこと」「次に挑戦したいこと」を話し合う。
- 友達とペアになり、お互いの良かった点を伝え合う。
次回へのつなげ方
- 「次はどんな泳ぎ方をもっと練習したい?」と考えさせ、学びを継続させる。
- 家庭でできる簡単なストレッチや陸上トレーニングを紹介する。
5. 授業のポイント
水泳運動の楽しさを伝える工夫
- 水に入ることへの恐怖心をなくし、楽しみながら慣れさせる。
- ゲーム要素を取り入れ、遊びながら技術を向上させる。
- 「できた!」という達成感を大切にし、児童の自信を育てる。
児童の成長に合わせた指導
- 水に慣れていない児童には、水遊びや顔つけの練習から始める。
- 得意な児童には、フォームの改善やスピードアップの課題を与える。
- 息継ぎが苦手な児童には、浮かびながらゆっくりと練習させる。
個別対応の工夫
- 水が怖い児童には、浅い場所での練習から慣れさせる。
- クロールの息継ぎが苦手な児童には、ボビング(呼吸のタイミングを取る練習)を行う。
- 速く泳ぎたい児童には、ストリームライン(抵抗を減らす姿勢)を意識させる。
6. 授業の工夫例
水に慣れるための工夫
- 水中じゃんけん:顔をつけたり潜ったりしながらゲームを行う。
- バタ足競争:浮き具を使いながら、楽しくキックを練習する。
- 水中探検ゲーム:プールの底に置かれた物を拾う遊び。
泳ぐ力を高める工夫
- グライド練習:けのびを長くすることで、抵抗を減らして進む。
- リズム呼吸練習:息継ぎのタイミングを意識しながら泳ぐ。
- 距離チャレンジ:泳げる距離を徐々に伸ばし、達成感を味わう。
水の安全を学ぶ工夫
- 浮き身の練習:水に浮くことの重要性を学ぶ。
- ペアレスキュー練習:助けを呼ぶ方法や、救助の基本を学ぶ。
- 水辺の安全講習:海や川での危険を知り、安全な行動を考える。
ICTを活用する
- 動画でフォームを確認:泳ぎ方を録画し、改善点を見つける。
- スローモーション分析:ストロークやキックの細かい動きを確認。
- 水中カメラを活用:実際の泳ぎを別の視点からチェックする。
まとめ
水泳運動の授業では、児童が「水に親しみ、安全に楽しく泳ぐ」ことを目標に、技術を段階的に習得できるよう工夫することが大切です。水に対する恐怖心をなくし、自信を持って泳げるようになる授業を展開しましょう。