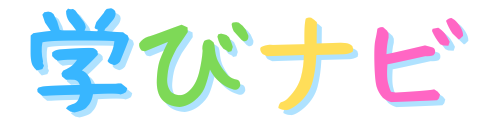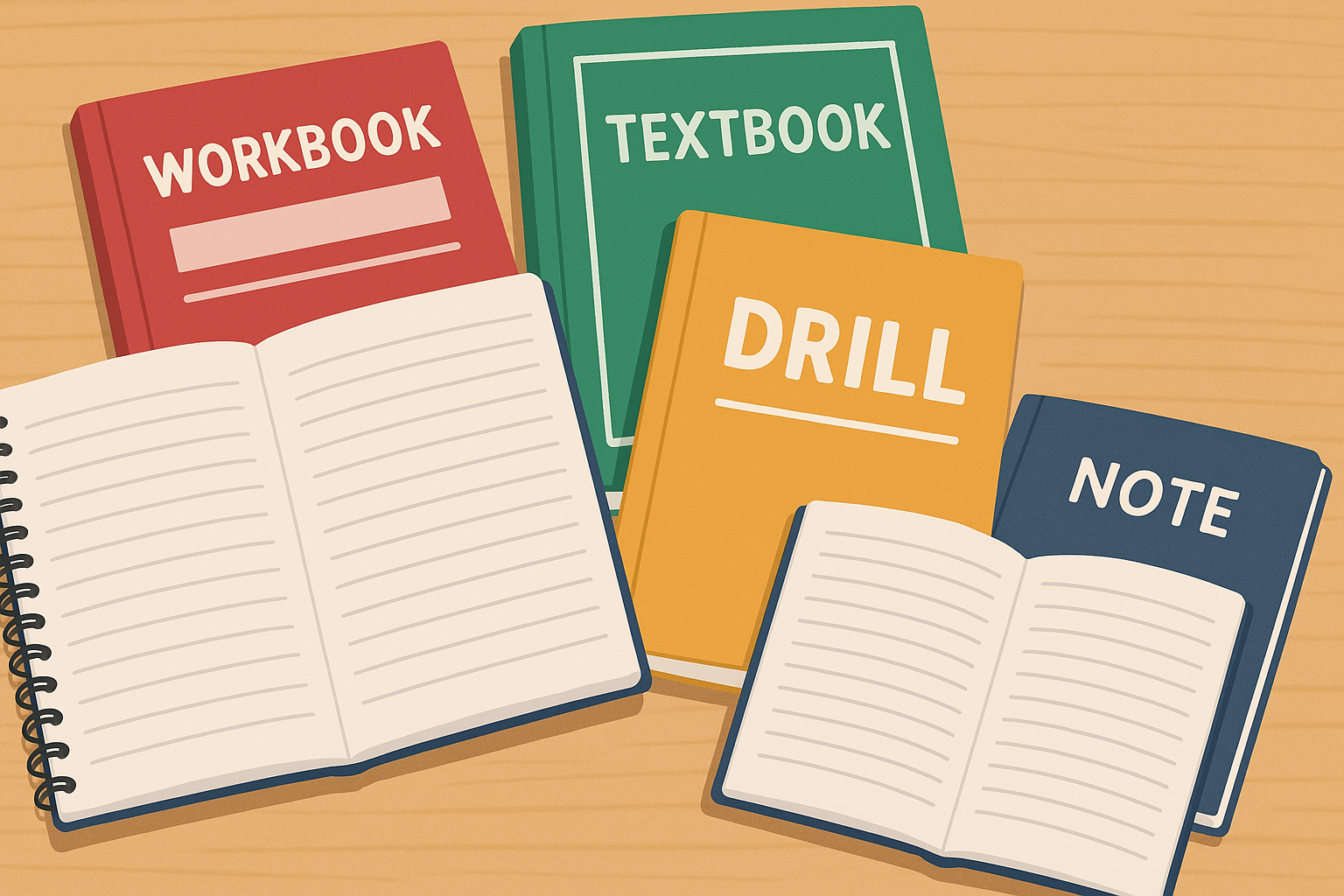新学期が始まる4月上旬、多くの小学校では「教材採択」が行われます。これは、子どもたちが1年間使用する教材(ドリル、副教材、テスト、ノートなど)を選定・発注する大切な作業です。本記事では、特に教員向けに、教材採択の基本から、教材ごとの選定ポイント、特に「テスト類」の選び方までを詳しく解説します。
1. 教材採択とは?
教材採択とは、学校現場で使用する各種教材を選び、決定するプロセスのことを指します。文部科学省の検定を受けた教科書は各自治体で採択されますが、それ以外のドリル・副教材・テスト・ノートなどは、学校ごとの裁量で選ぶことができます。
学校によっては「教材選定委員会」「教材部会」などを設け、各学年・教科担当が集まり、教材の使用目的や指導計画との整合性を確認しながら慎重に選定を行います。
2. 教材採択の年間スケジュール(一般例)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1月〜2月 | 教材見本の取り寄せ・教員による試用・情報収集 |
| 3月 | 学年や教科部会での協議 |
| 4月上旬 | 教材選定会議での正式決定・発注 |
| 5月以降 | 使用開始(学年によって異なる) |
早めの準備が、質の高い教材選定に繋がります。特に新教材の導入を検討している場合は、1月ごろからの見本依頼と試用が鍵となります。
3. ドリル・副教材の選び方
① ドリルの選定ポイント
- 教科書準拠かどうか:指導との連携が取りやすくなる
- 児童の実態に合っているか:発展・補充教材が必要な児童にも対応できるか
- 繰り返し練習ができるか:計算・漢字ドリルでは特に重要
- 保護者が見て理解できる形式か:家庭学習への接続がしやすいか
② 副教材の選定ポイント
- 教科の理解を深める補助になるか:図解・写真・QRコードでの動画連携など
- ICT教材との併用が可能か:紙媒体+デジタルのハイブリッド学習
- 評価や記録が取りやすいか:ポートフォリオ型の教材も注目されています
4. 特に重要!テスト教材の選び方
① テストの種類と目的
- 単元テスト:教科書に準拠し、単元ごとの理解度を確認
- 実力テスト・到達度テスト:範囲を超えて実力を測る目的
- 観点別評価対応テスト:新学習指導要領に沿って、思考力・判断力・表現力などの観点別に評価ができる
② テスト選定のチェックポイント
- 教科書との整合性
- 同じ出版社・系列のテストは使いやすい
- 教科書の文言や設問形式に近いものが望ましい
- 観点別評価への対応状況
- 4観点(知識・技能/思考・判断・表現/主体的に学習に取り組む態度)での評価記録が取りやすい形式か
- 自動集計や観点ごとの分析が可能な別冊やアプリの有無
- 出題形式のバランス
- 知識系(選択・穴埋め)と記述系(作文・意見文など)のバランス
- 表やグラフ、資料を読み取る問題が含まれているか
- 採点のしやすさ・記録のしやすさ
- 回答欄が整理されており、採点負担が軽減できるか
- 成績一覧表や記録用紙がダウンロード可能か
※特に記述問題は、正解とするかどうかの基準が難しく、教員間での共通理解が必要です。単学級であれば教員一人で判断できますが、複数学級がある場合には、学級間で基準がぶれないように、テストごとに事前の相談や協議を行う必要があります。また、記述問題が多いと、丸つけに多くの時間を要し、日常の業務に支障をきたすこともあります。そのため、記述問題の量と質のバランスを考慮して選定することが重要です。
- ICT対応・Webサポートの有無
- テスト結果の入力で自動的に評価観点がグラフ化されるシステム
- 家庭と共有できるフィードバック資料があるか
③ 人気のテスト教材(例)
- 教育出版の「観点別テストシリーズ」
- 光村図書系列の「単元テスト+ポートフォリオセット」
- 啓林館の「テストdeスキルアップ」シリーズ
5. 教材採択の進め方と校内連携
教材採択は、学年・教科・管理職・事務など多くの関係者が関わるチーム作業です。スムーズに進めるためには、以下のような校内連携が重要です:
- 教科主任が中心となり、見本の取り寄せや比較表の作成を行う
- 学年会で実際に児童に使わせた試用結果を共有する
- 決定後は事務職員と連携して発注ミスがないようにする
6. 採択後に備えておきたいこと
- 教材の使い方マニュアルや研修会の確認:特にICT教材や新教材の場合
- 保護者への説明準備:使用教材の目的・特徴を伝えることで理解と協力を得る
- 活用例・授業展開の共有:教員間で使用例を共有すると活用の幅が広がる
まとめ
教材採択は単なる「発注作業」ではなく、子どもたちの1年間の学びを大きく左右する教育活動の一部です。特にテスト類の選定は、評価の質に直結する重要な作業となります。教科書との整合性や観点別評価への対応、ICTとの連携など、様々な視点からじっくりと選んでいきましょう。
「学びナビ」では、今後も教員の皆さまの教材選定や授業準備をサポートする情報を発信していきます。