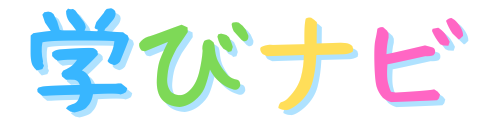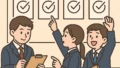はじめに
学校での避難訓練は、地震・火災・不審者などの非常時に備えて、児童生徒の命を守るための大切な活動です。
新年度が始まると、早ければ4月中に避難訓練が実施される学校も少なくありません。
新人教師にとっては「初めて指導に関わる避難訓練」に不安を感じることもあるでしょう。
この記事では、
✅ 避難訓練の目的と基本的な流れ
✅ 指導前・当日の動き・振り返りのポイント
✅ よくある失敗とその対処法
について丁寧に解説します。
【1】避難訓練の目的とは?
学校での避難訓練の主な目的は以下の3つです:
- 命を守る行動を身につけること
- 非常時に落ち着いて行動できるようにすること
- 児童の安全を確保するための教師間の連携を確認すること
📌 「おおごと」ではなく「日常の大切な訓練」と捉えることがポイントです。
【2】事前準備|訓練前に確認しておくべきこと
避難訓練は準備が8割です。事前の確認をしっかりしておくことで、当日慌てることが減ります。
✅ 学年・学級の集合場所と避難経路
✅ 教室に掲示されている避難経路図の確認
✅ 非常ベルや放送の合図の種類と意味
✅ 担当業務(先導・誘導・人数確認など)の役割分担
✅ 特別支援が必要な児童やけがをしている子への対応
✅ 雨天時の対応(グラウンドが使えない場合など)
🧑🏫 教室での並び方を事前に練習しておこう
避難行動は「教室で並んでから出発」するのが基本です。しかし、初めてのクラスでは、並ぶ順番が分からず戸惑う子も多くいます。
→ 避難訓練の前に、実際に並ぶ練習をしておくことが重要です。
✅ 並ぶ位置を黒板やホワイトボードに書いておく
✅ 廊下に並んでみる練習も1回はしておく
👥 バディ制度を使う場合の注意点
一部の学校では、低学年などを中心に「バディ制(2人1組で行動)」を取り入れています。
その場合:
- 誰と誰がバディなのかを子ども自身が把握しておくことが大前提
- バディ同士で「どこに立つ」「どう動く」かを事前に教えておく
- 学級掲示で常に確認できるようにしておくと安心
📌 緊急時にはパニックになりやすいため、日頃からの習慣化がポイントです。
💡事前に学年主任や養護教諭と情報共有しておくと安心です。
【3】訓練当日の流れ(基本)
以下は地震を想定した避難訓練の一例です。
- 放送による地震発生の知らせ(身の安全確保)
- 放送による避難指示(ヘルメット・防災ずきんの着用)
- クラスごとの避難開始(整列・移動)
- 避難完了(点呼・人数報告)
- 校長先生や防災担当者からの講評
📣 ポイントは「静かに・素早く・安全に」。
【4】指導のポイント|子どもたちにどう伝えるか?
✅ 最初に「なぜ訓練が必要なのか」を伝える
「この訓練は、みんなの命を守るためにとても大切なことです」 → 意識を変えるだけで、行動の真剣さが変わります。
✅ 「静かに・早く・整然と」が基本
→ 冗談を言ったりふざけたりする子がいたら、その場でしっかり指導します。
✅ 指導の言葉は「端的で明確に」
→ 「右手をあげて、並びましょう」など、短く・わかりやすく伝える
✅ 点呼・人数確認は何より重要
→ 移動中も目を配り、並び方の乱れがあれば立ち止まって整える勇気を持ちましょう
【5】よくある失敗とその対処法
❌ 放送が聞こえなかった
→ 事前に「放送が聞こえなかった場合の動き」も伝えておく
❌ クラスがばらけてしまった
→ 「どこで止まる」「どこを曲がる」など、細かく下見しておく
❌ 指導が不安で声が小さくなる
→ 最初の声出しが大切!自信がなくても「大きな声」で指示するだけで子どもたちが落ち着きます
❌ 点呼ミスが発生した
→ 一人ずつ名前を呼ぶ or 担任が数えながら目視確認。名簿と人数だけに頼らず、顔を見て確実に!
【6】振り返りも大事!避難訓練は“やりっぱなし”にしない
避難訓練のあとは、子どもたちと一緒に「良かったところ・改善点」を話し合いましょう。
✅ 何がよくできたか?(静かにできた・早く集まれた)
✅ どんな場面で困ったか?(靴が脱げた・迷ってしまった)
✅ 次に同じことが起きたら、どうすればよかったか?
📌 一緒に振り返ることで、防災意識がぐんと高まります!
【7】まとめ|“備え”が命を守る
避難訓練は、単なる形式的なイベントではなく、非常時に命を守るための本番さながらの練習です。
新人教師にとって最初は緊張する場面かもしれませんが、
✅ 事前準備をしっかり行い、
✅ 子どもたちに真剣に伝え、
✅ 自分の動きにも“自信”と“冷静さ”を持つ
ことが何よりも大切です。
あなたの一言が、子どもたちの命を守る“行動”につながります。
安全・安心な学校生活のために、今日の一歩をしっかりと!