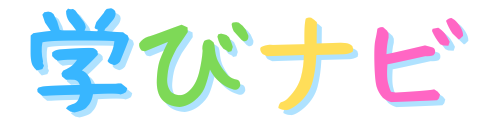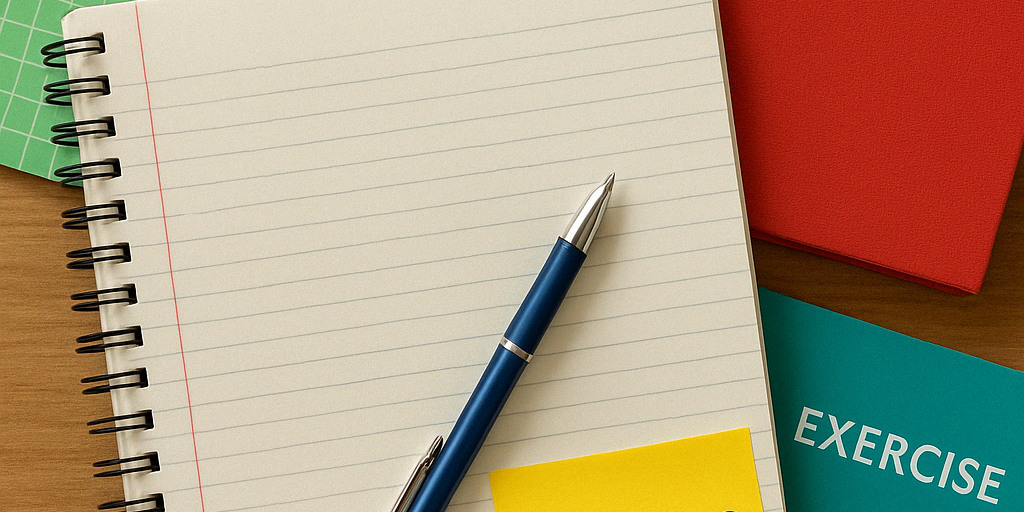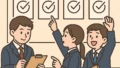はじめに
4月、新年度のスタートに向けて新人教師がまず直面するのが「学級経営案」の作成です。
学級経営案とは、担任として1年間どのように学級を運営していくかをまとめた計画書であり、学校に提出する公式文書でもあります。
「何を書けばいいのかわからない」 「フォーマットはあるけど内容に悩む…」 という新人の先生に向けて、この記事では:
✅ 学級経営案の目的と意義
✅ 基本的な構成と項目の意味
✅ 各項目の具体的な書き方と記入例
✅ 書く際に押さえるべきポイント
をわかりやすく紹介します。
【1】学級経営案とは?その目的と役割
✅ 学級経営案の目的:
- 担任が目指す学級像を明確にする
- 教育活動全体の見通しを立てる
- 学校全体の経営方針との整合性をとる
- 学年・他教職員との情報共有のための資料になる
📌 “自分なりの方針”を明文化することで、日々の実践がブレなくなります!
【2】基本的な構成(一般的な例)
学校や地域によって若干の違いはありますが、多くの場合以下のような項目で構成されています:
- 学級の目標・ビジョン
- 学級経営の基本方針
- 教育課程の重点と配慮事項(教科指導)
- 生活指導・特別活動の指導方針
- 児童理解と支援(個別の配慮)
- 学習評価・通知表の考え方
- 家庭・地域との連携
- 行事や年間スケジュールへの対応
【3】各項目の書き方と記入例
✍️ ① 学級の目標・ビジョン
「どんな学級にしたいか」を簡潔に書く
📌 学級目標は、自分の学級の児童が学校目標を達成するために必要な姿や行動を具体化したものです。 → まず学校全体の目標を確認し、それを児童の発達段階や実態に応じて言い換えましょう。
【記入例】
- (学校目標:自ら考え 行動する子) → 学級目標:「自分からあいさつ・チャレンジ・協力できるクラス」
- (学校目標:やさしさ・つよさ・かしこさを備えた子) → 学級目標:「思いやりをもち、学びに向かい、助け合える学級」
✅ キャッチコピー形式+簡単な補足の形もおすすめ!
✍️ ② 学級経営の基本方針
学級運営で大切にする「軸」を明記する
【記入例】
- 子ども一人ひとりの違いを認め合い、個性が活きる学級づくりを目指す。
- 自主性と責任感を育てる日常指導を中心に据える。
- 学習と生活の両輪をバランスよく支える。
✍️ ③ 教育課程の重点と配慮事項(教科指導)
特に力を入れたい教科や授業スタイルについて述べる
【記入例】
- 国語では「話す・聞く」活動を重視し、発表力の育成を図る。
- 算数ではつまずきを早期に発見し、個別に補充を行う体制をつくる。
- ICT機器を活用し、主体的・対話的な学びを促す。
✍️ ④ 生活指導・特別活動の方針
日々の生活習慣・集団活動・自治活動に対する考え
【記入例】
- あいさつ・時間・忘れ物など、生活の基本習慣を定着させる。
- 委員会や係活動を通じて、社会性や責任感を育む。
- トラブル対応では「予防」と「対話」を大切にする。
✍️ ⑤ 児童理解と支援
配慮を要する児童への支援や、児童理解の方針
【記入例】
- 毎日の声かけ・観察・記録を通じて個の実態をつかむ。
- 支援が必要な児童には、特別支援コーディネーターや養護教諭と連携して支援する。
- 心の動きに気づけるよう、日記やふりかえりを活用する。
✍️ ⑥ 学習評価・通知表の考え方
「学力」だけでなく、「態度」や「努力」も含めてどう評価するか
【記入例】
- 過程を評価するため、ワークシート・提出物の活用を重視する。
- 授業中の発言や協働の様子など、日常的な観察を記録に残す。
- 通知表の所見は、具体的かつ前向きな表現を心がける。
✍️ ⑦ 家庭・地域との連携
保護者との関係構築や地域資源の活用について触れる
【記入例】
- 保護者との信頼関係を築くため、電話・面談・連絡帳を丁寧に活用する。
- 地域ボランティアやPTAと連携し、学習活動を充実させる。
✍️ ⑧ 行事や年間スケジュールへの対応
行事の位置づけや、年間計画の中で意識したい点を記述
【記入例】
- 行事を「成長のきっかけ」として位置づけ、子どもの主体性を大切にした運営を行う。
- 行事と日常との切り替えを明確にし、学習リズムの維持を図る。
【4】書くときのポイント&注意点
✅ 学校・学年の方針と整合性をとること
→ 自分だけの独自性を出しすぎると浮いてしまう可能性も
✅ 「できそうなこと」「やれること」を書く
→ 理想論ではなく、自分が実行できる範囲に落とし込む
✅ 読み手(管理職・学年主任)を意識する
→ 論理的に、簡潔に書くことで「信頼」につながる
✅ 形式面も丁寧に
→ 誤字脱字なし/フォーマット統一/適切な文末表現(です・ます)
【5】まとめ|学級経営案は1年間の“設計図”
学級経営案は、担任にとっての「コンパス」。
完璧である必要はありませんが、1年間を通して「何を軸に学級をつくっていくのか」を可視化することで、 日々の指導が安定し、迷いが減ります。
✅ 自分の言葉で
✅ 現実的にできることを
✅ 子どもたちの成長につながる視点で
書くことが、よりよい学級づくりへの第一歩になります。
自信を持って、あなたらしい経営案をつくってみてください!