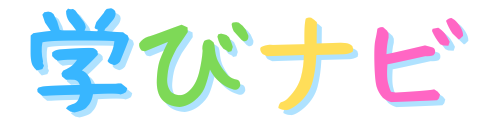はじめに
週案(しゅうあん)とは、1週間の教育活動の計画を立てるための文書であり、学年主任や管理職に提出する「指導の見通し」の記録でもあります。
特に新人教師にとっては、毎週の提出に追われながら「何を書けばいいのか分からない」「どうすれば早く書けるのか」と悩みがちです。
この記事では:
✅ 週案の目的と役割
✅ 書き方の基本構成と記入例
✅ 書く際の注意点と時短のコツ
✅ よくある質問とトラブル対処法
を分かりやすく解説します。
【1】週案とは?目的と役割
✅ 週案の主な役割:
- 1週間の学習内容と活動の見通しを立てる
- 教科ごとのねらいや指導法を明確にする
- 管理職・学年主任との共有・相談の基礎資料となる
- 指導の記録として保存・活用できる
📌 「自分の指導を言語化し、振り返ること」が最大の目的です。
【2】週案の基本構成とフォーマット
学校によって若干異なりますが、一般的な週案には以下の項目が含まれます:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | 月〜金の5日間の記載 |
| 時間割 | 各日・各時間帯の授業内容 |
| 教科・領域 | 国語、算数、生活、図工など |
| 学習のねらい | その時間で児童に何を身につけさせるか |
| 学習活動 | 教師の指導・児童の活動内容 |
| 評価の観点 | 観察・発問・ワークチェックなど |
| 備考欄 | 行事、変更、配慮事項など |
| 反省欄 | 1週間の授業や指導を振り返った気づきや改善点 |
📌 ExcelやWordで編集できるテンプレートを使うと便利です!
【3】週案の記入例(国語・算数)
● 国語(3年・説明文)
- 学習のねらい:段落ごとの要点を読み取り、文章全体の構成を理解する。
- 学習活動:音読→段落の要点探し→全体の構成を確認→ふり返り
- 評価:発言の様子、ワークシートの記述内容
- 備考:話し合い活動を行うため、机配置を工夫する
● 算数(4年・角の大きさ)
- 学習のねらい:分度器の使い方を知り、角の大きさを正しく測る。
- 学習活動:導入(実生活の角)→分度器の使い方説明→測定練習→ふり返り
- 評価:測定結果、友達との説明のやりとり
- 備考:分度器を忘れた児童には貸し出し対応
【4】書くときのポイントと注意点
✅ 「ねらい」は教科書や指導書から確認しておく
→ 学習指導要領や単元の目標とつながっていることが大切
✅ 「活動」は“教師の指導”と“児童の活動”をセットで書く
→ 教師が何をして、児童が何をするかを明確に
✅ 「評価」は観察・ワーク・発表など具体的に書く
→ 曖昧な記述(例:理解できたか)ではなく、何で見るかが重要
✅ 「備考」には行事や特別支援の配慮なども忘れずに
→ 給食指導や清掃分担、行事準備なども記載しておくと共有に役立ちます
📌 年間指導計画に授業の目標や主な学習内容が載っている場合が多く、そこからコピーして週案に活用するのが時短のコツです。
→ すでに計画されている内容をそのまま使えば、書く時間を短縮できます。
✍️ 週案に時間を取られすぎないよう、必要最低限の記載にとどめ、その分の時間を授業準備や教材研究に充てた方が効果的です。
✅ 「反省欄」の活用ポイント
週案には「反省欄」が設けられている学校も多くあります。
反省欄には:
- 児童の理解度や授業の様子に対する振り返り
- うまくいった指導法や工夫した点
- 改善すべき課題や次週への課題
- 特別な配慮が必要だった児童への対応記録
などを簡潔に記載します。
📌 成功体験だけでなく、小さな課題や違和感も書いておくと、次の授業改善に役立ちます!
【5】時短のコツ&便利な工夫
✅ 単元計画をベースに週案を作成すると効率的
✅ 前週の週案をコピーして編集すればミスも減る
✅ 同じ学年の先生と分担・共有(Googleドライブなど活用)
✅ 決まった表現は定型文として保存しておく
📌 毎週ゼロから書かない!「型を持つ」ことが時短の第一歩です。
【6】よくある質問とトラブル対処法
Q. 書いた週案が返ってきて赤字だらけでした…
→ 指摘の意図を理解し、次回に反映。経験を重ねることで精度は上がります!
Q. 毎週間に合わない!
→ 水曜や木曜のうちに7割完成を目指すと金曜に焦らずに済みます。
Q. 週案が「ただの予定表」になってしまっている気がする…
→ 活動の意図や評価をきちんと記述すれば、意味のある計画に変わります!
【7】まとめ|週案は“振り返り”と“見通し”の両輪
週案は、単なる業務ではなく
✅ 自分の授業を見つめ直す機会であり、
✅ 学年や学校との連携の道具でもあります。
「面倒だからとりあえず書く」ではなく、 「自分と子どもの1週間をつなぐツール」として活用する意識が大切です。
必要最低限でいい。大切なのは、それを元により良い授業を準備できるかどうかです。
初めての週案作成でも、ポイントとコツを押さえれば大丈夫! あなたの学級づくりを支える力になります。